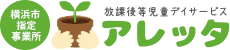今日も皆さんと一緒に、発達障害等に関する学びや情報交換の場所となることを願って投稿させて頂きます。 今日のトピックは「発達障害と動物」についてです。
近年は「ペットブーム・ねこブーム」と言われ、TVやネットでも話題や動画がたくさん登場します。ペットショップや動物園では、子供も大人も誰もが無邪気になって、ほっこり笑顔で一心に動物を見つめます。
医療や福祉の現場などで、動物と触れ合う「アニマルセラピー」ということが行われますが、発達障害にも有効なのでしょうか?単にペットを飼うのとは違うのでしょうか?危険など注意点は無いのでしょうか?
アニマルセラピーによる効果と、発達障害との相性を実例も含めて、メリット・デメリットを確認します。
目次
アニマルセラピーとは

日本アニマルセラピー協会という団体があります。そこでは「アニマルセラピー」について、次のように紹介されています。
アニマルセラピーとは、動物と触れ合うことで精神的・身体的に機能を向上させることにより、生活の質を向上させる療法のことを言います。
日本アニマルセラピー協会
アニマルセラピーの種類
「アニマルセラピー」という言葉は、日本で作られた造語です。活動と目的により分類される3つのタイプを、正式名称と共にご紹介します。
動物介在療法(AAT:Animal Assisted Therapy)
動物を用いた医療活動で、医療従事者や有資格者が療法として行うものです。
社会に馴染めない引き籠りや不登校の人達、病気や障害を持つ人達などが、動物と触れ合うことにより不安やストレスを軽減して、精神的な健康を取り戻すためや、生活の質的向上を目的とします。
動物介在活動(AAA:Animal Assisted Activity)
人と動物が触れ合う場を提供する活動のことで、資格を持たないボランティアなどでも行える、広い意味でのアニマルセラピーです。
動物に触れたいという自発性や意欲を促したり、話かけたり戯れることで笑顔などの豊な表情を引き出します。発声と会話や運動機能の改善といった、生活の上での良い変化が期待でき、療法よりも生活の質の向上に重点を置いています。
動物介在教育(AAE:Animal Assisted Education)
動物を通して命の尊さを学ぶ教育プログラムのことで、学校や施設に、動物と共にインストラクターやボランティアが訪問するスタイルが多いです。
団体での移動や、大勢が一緒に学ぶのが難しい場合でも、授業の一環として導入できるので、広く多くの場で活用されています。
セラピーアニマルの種類
アニマルセラピーに用いる動物は、セラピーアニマルと呼び、基本的には人に慣れやすく、躾もできる知能を持つ動物に適性がありますが、思った以上に様々な動物が用いられています。
犬
犬は、一番一般的で代表的なセラピーアニマルです。セラピードッグとしての訓練や、アニマルセラピストとしての民間資格なども確立されています。
大きさや犬種などバリエーションが豊富です。人との長い共存の歴史が物語る、安心して触れ合える動物でしょう。
猫
猫は勝手気まぐれで躾にも従順ではないので、一見セラピーアニマルに不向きな印象が有るかも知れません。しかし意外にも、その気ままさが精神疾患、中でも特にうつ病の患者には良い効果を持つようです。
自己投影からの共感を呼び、ありのまま自由でも良いことを肯定する気持ちにしてくれ、患者はプレッシャーから解放されるといいます。
馬
ホースセラピーは、以外にもアニマルセラピーの中で一番古く、歴史があるものです。1453年のローマ時代において、戦争での負傷兵にリハビリとして行われた、乗馬療法が起源です。
これは、現在でも日本や海外で治療法として確立され、用いられています。
イルカ
クジラやイルカの仲間は、コミュニケーションや餌を探すために、超音波を発する器官を持っており、その超音波が人にもリラックス効果をもたらすという研究結果が出ています。
魚類
アクアリウムセラピーといって、幻想的に美しく設えられた水槽を眺めることで、精神的なリラックス効果を生み、ストレスを和らげるものです。
他には、ドクターフィッシュという魚を用いて、手や足の角質を食べさせて突つかれる刺激を体験するものがあります。
その他
ハムスター、モルモット、ウサギ、ヒツジ、ヤギ、ウシ、ブタ、サル、小鳥、爬虫類、両生類、昆虫、植物など、様々な生き物が用いられることがあります。
参考元:日本アニマルセラピー協会、介護の123、ONMEGA、SPOLABO
アニマルセラピーの効果

アニマルセラピーは、精神的・身体的・社会的な面で、様々な効果が期待できると考えられています。その一例をご紹介します。
- 表情が明るくなる
- 不安やストレスを軽減する
- 情緒面の安定が図れる
- 歩きたい、動きたいという意欲がわく
- 自発性が向上する
- 戯れたり世話をしながら身体の運動量が増える
- 世話をするなどの役割を持つ
- 自己肯定感を高める
- 動物の話題を通して会話が増える
- 発声のリハビリになる など
効果を解説したYouTube動画も、ご覧ください。
実例として、アメリカの農場体験と、日本のペットを飼った例のブログ、そして自閉症の少女のYouTube動画を、それぞれご紹介します。
参考元:OG介護プラス、たーとるうぃず、笑う門には福が来るブログ
アニマルセラピーの注意点

生き物が相手なので、特に訓練されていない動物には、危険などのリスクが伴うことも考えられます。また、動物慣れしていないため衝動的に恐れたり、力加減をコントロールできない子が小動物を傷つけたりする危険などもあります。
人間に対して
- 恐怖症
- 動物アレルギー
- 感染症や衛生面での問題
- うなる・吠えるなどの鳴き声
- 引っ掻きや噛み付きなどによる怪我 など
動物に対して
- 動物が受けるストレス
- 疲労の蓄積
- 運動不足や肥満になる可能性
- 人間からの感染症
- 異物を食べる
- 環境破壊 など
参考元:OG介護プラス、
アニマルセラピーを受けるには

アニマルセラピーを実施している団体を、ご紹介します。ボタンをクリックすると、ホームページがご覧になれます。動物の種類や費用など、実施内容の詳細については、各団体にご確認ください。
放課後デイサービス アレッタの紹介

放課後デイサービス アレッタは横浜市を拠点とし、子どもたちの自立や健全な育成のために、障害児と保護者をサポートしています。
「自分の意思で行動する子」を育てようと、指導員はキッカケを与える助け手として接しながら、子供たち自らが選択し、学べる環境を提供しています。
「自分でできる」という自信を持たせ、将来に安心して暮らすことができるようになるための、創意工夫を込めたお手伝いをしていますので、是非上記リンクよりご覧ください。
まとめ
動物が人間に与える影響は、アニマルセラピーに代表され、それは、発達障害にも同様です。
目的により、治療・活動・教育と分かれており、それぞれに優れた良い効果が認められています。
セラピーアニマルとして用いられる動物は、犬、猫、馬をはじめ、様々な動物が用いられています。生き物である以上はリスクもあります。それは、人へも動物へも双方向にあるので、留意しなければなりません。
それでも、アニマルセラピーの効果は絶大なので、利用するには、正しく専門機関を利用するのが良いでしょう。