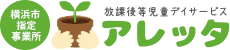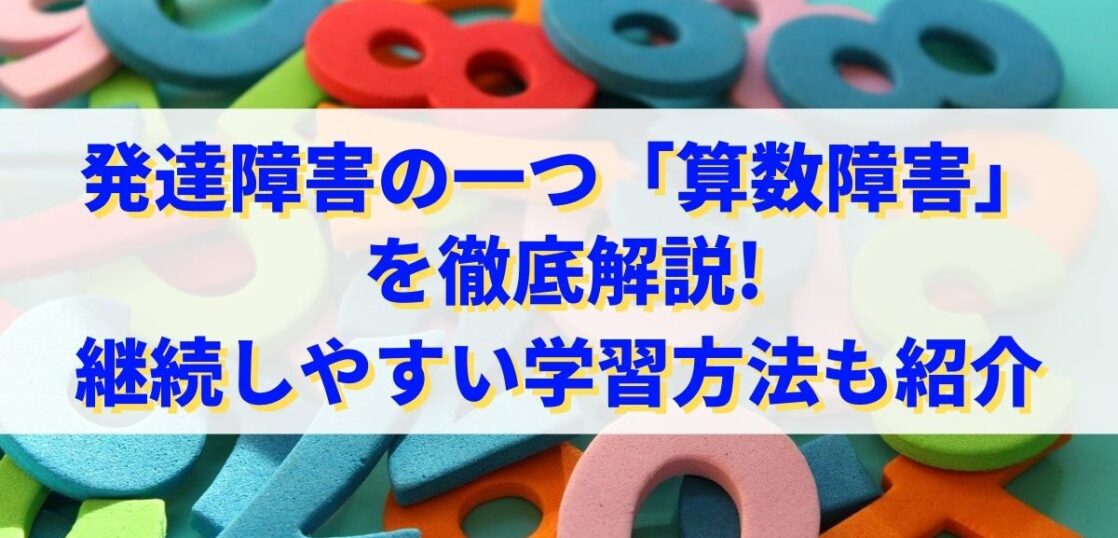今日も皆さんと一緒に発達障害等に関する学びや情報交換の場所なることを願って投稿させて頂きます。
今日のトピックは「発達障害と算数の関係」についてです。
お子さんの算数学習が進まずに「周りと比べて我が子は遅れをとっている…」と心配してしまう保護者の方はいらっしゃいませんか?
もしかしたらお子さんは算数障害なのかもしれません。
今回は発達障害の一つである算数障害の特徴と、算数障害の人でも算数が身につけられる対処法をお伝えします。
目次
算数障害は学習障害(LD)に該当
算数障害は発達障害の一つ学習障害(LD)に分類されており、主な特徴は3つあります。
- 九九が中々覚えられない
- 簡単な計算問題が苦手
- 文章題が苦手
小学校へ入学し徐々に勉強への遅れが見える頃、算数障害は上記のような特徴が発覚すると言われています。
次項では算数障害の3つの特徴を確認していきます。
(補足)学習障害については、下の記事で詳しく説明していますのでこちらも合わせてご覧ください。
九九が中々覚えられない
九九を覚える時に算数へ苦手意識を持ってしまう人は多いのではないでしょうか?
九九は「覚える」「暗算する」を同時に行わなければならないため、頭をフル回転しなければなりません。
算数障害含む発達障害を抱えている人はマルチタスクが苦手な場合が多く、九九に対して苦手意識を持つ可能性があります。
マルチタスクを要求される他、覚えられない要因の一つとして、九九の独特の「音」もあると想定できます。
1の段の九九を確認する時、普段聞きなれない「音」と数字が結びつかないお子さんはいらっしゃいます。
1×1=1(いんいちがいち)
1×2=2(いんにがに)…
慌てずにゆっくり身につけていきましょう!
九九ができるようになるには?
九九ができるようになるには、九九のカードや表などで音だけではなく、目で確認できるとより理解しやすいようですね。
以下の動画のように、カードを見ながら遊び感覚でリズムに合わせて覚えてみましょう。
簡単な計算問題が苦手
算数障害の人は、簡単な計算問題で数字という文字の認識と数量の認識が統合できないため問題が解けない場合が多く発生します。
【数字と数量が噛み合わない例】
1+2=3
●と●●を合わせると●●●
例のように、数字と数量の違いがわからないと算数問題で解答に時間がかかってしまいます。
数量の認識ができるようになるには?
どうすれば数字を数量として認識できるようになるのでしょうか。
動画教材を使用
一つの方法として、以下のような動画教材を使用し、数量と数字を覚える方法があります。
知育教材を使用
教材を使用する場合は段階的に取り組み、最初は難易度の低いものから選んでください。
あれもこれもと一気に取り組むと混乱してしまいます。
- 指やブロックを使って、数量が認識できるように学習する
- 慣れたらおやつの卵ボーロを使って「3つ食べるから出して」と声かけし、袋から3つ出すというような訓練をする
- 数字カードを用意して「今から出す数字を指でしてみてね」といった問いかけに答えてもらう
数量の認識が進めば、1桁の足し算や引き算は、無理なくできるようになります。
文章問題が苦手
文章問題は文章全体を読み解く必要があるため、応用問題として使用されやすい算数問題です。
【文章問題の一例】
お母さんが12円持っています。お父さんから3円もらいました。
お母さんは、何円持っていますか?
文章問題を解く時に、算数障害の人は問題の状況を思い浮かべられず計算が進みません。
原因は数字の行き来がわからない、読解力が低い、などが挙げられます。
文章問題を解けるようになるには?
文章題ができるようになるには状況への理解が必要です。
例として、保護者の方は果物のイラストや果物など数えられる実物を用意してください。
文章を読みながら動かしどういう状況なのかを理解させます。
目で見て状況を把握できるようになれば、文章問題になってもイメージしやすく、効果が期待できるでしょう。
算数への苦手意識を減らそう

算数に対して少しでも苦手意識を減らすため、普段から保護者ができる対策をお伝えします。
日常生活に算数を取り入れる
算数は日常生活のさまざまな場面で取り入れが可能です。
例えば買い物の時にいくらのお菓子を何個買ったかを問題にすると、生活の中で学べますね。
トイレットペーパーは4つずつ3段に積まれた状態で、パッケージされているものがあるので、立体認識や掛け算の勉強を取り入れてみるといいでしょう。
実際ノートを開いて勉強するよりも、日常生活の中で実体験するほうが記憶に残りやすい人もいます。
普段から買い物で簡単な算数トレーニングを取り入れると、苦手意識を減らす効果を期待できます。
算数にとらわれず、認識力を鍛える
お子さんの算数に対するハードルを下げて勉強をしてみませんか?
例えば小学生低学年であれば、昔習っていた年中用の絵で表現されたようなイラストの描かれた問題を解いてみると認識力が鍛えられます。
以上のように算数と言う概念にとらわれず、問題数をこなして認識力を鍛えることも大事です。
年中用の問題が見つからない場合は、計算カードを使った遊びを日課にしてみるのもいいでしょう。
さらに学習障害について知りたい方に向けて専門書を紹介します。
算数の教え方そのものについても掲載されており参考になるかもしれません。
算数でつまづいたら原因を分析しよう

もしお子さんが算数でつまづいてしまったら、そのままにせずどこでつまづいてしたのか分析してみてください。
「九九は覚え1桁の掛け算はできるようになったけれど……次に進めない」などです。
できた問題とできなかった問題の違いを見つられると解決法が見つかるかもしれません。
例えば「なぜ、2×10ができないのか?」に対する教え方は一つではなく、3通りあります。
- 2×9=18
その次の数字10になると…
2×9=18、2×10=20
- 2が10こあるから…
2+2+2+2+2+2+2+2+2+2=20
- 2×10の0を指で隠して…
2×1=2、十の位の数字は2になりました。1の位は隠していた0をでした!
上記のように個人に合わせた考え方の提案ができるのです。
それぞれお子さんの理解や認識に合わせた教え方をしていれば、算数の苦手は克服に期待できます。
教え方がわからなければ専門家に依頼しよう

お子さんの算数の学習に対し、保護者一人では対処できないようなら、学習専門の放課後等デイサービスを利用してみると発達障害児向けの学習方法が確認できます。
例えば数字ブロックやカードだけではなく、すごろくやゲームを使って理解を深めるなど、一般の人では想像ができないやり方で導いてくれるかもしれません。
学習専門のデイサービスではなくても大丈夫です。
自宅ではなくデイサービスで宿題を行うなど学習環境を変えるだけでも、お子さん一人で算数に取り組める可能性はあります。
勉強に特化していなくても発達障害の専門職が手助けをすれば子どもの理解が進みます。
発達障害があるから勉強ができないとあきらめる前に試してみませんか?

放課後等児童デイサービスアレッタには子どもたちそれぞれの発達障害を理解し、個々に対応してくれる専門のスタッフが常駐しています。
保護者からの相談にも親身になって対応いたします。悩みを1人で抱え込まず、相談してみませんか?
まとめ
お子様がどうしても勉強が苦手で理解するのに時間がかかっていると保護者の方は心配になってしまいますよね。
ですが保護者の方以上に子ども自身が不安になっています。
不安を取り除くにはできることから始め、「できた」を積み重ねて上げてみてください。
支援学級に通うお子さんは算数の授業を教えてもらうようにすれば、クラスメイトと比較してできないと落ち込むことは減少します。
子どものストレスを減らし、健やかな学校生活を送れるようお子さんを見守っていきましょう。