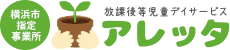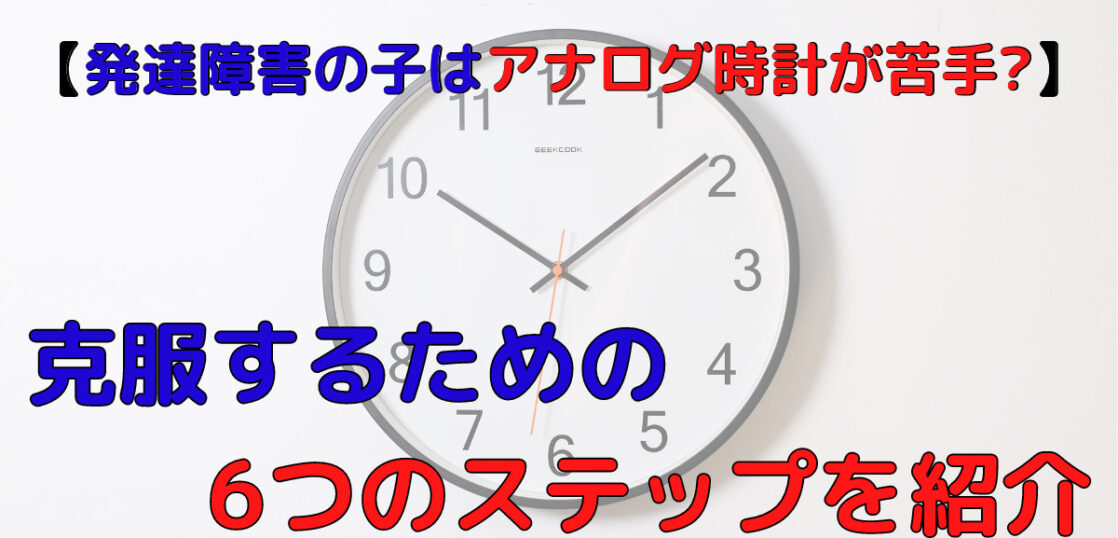今日も皆さんと一緒に発達障害等に関する学びや情報交換の場所なることを願って投稿させて頂きます。
今日のトピックは「発達障害と時計」についてです。
そこで今回は、発達障害の影響で時計を読むことが困難な場合の対応策についてお伝えします。
訓練により時計が読めるようになる子もいれば、どんなに努力しても読めない子もいます。
それぞれのケースについて対応策が考えられるので、具体的にみていきましょう。
目次
なぜ発達障害の子供はアナログ時計が苦手なの?

なぜ、発達障害の子供はアナログ時計を読むことが苦手な場合が多いのでしょうか?
発達障害のどのような面からの影響なのか紹介していきます。
【発達障害とは?】
- 学習障害
- 自閉症
- アスペルガー症候群
- 注意欠陥多動性障害
- その他広汎性発達障害
発達障害は、生まれつき脳の機能が通常と異なることにより生じる障害のことをいいます
その中でも考えられる影響として、主に次の2つの側面があります。
学習障害による影響
まずは学習障害による影響です。
その症状は子供によりさまざまですが、下記の症状があります。
【学習障害とは?】
- 聞く
- 話す
- 読む
- 書く
- 計算する
※上記、一つまたは複数において中々習得できない状態
つまり、アナログ時計が苦手な場合、算数の教科で「時計を読む」という分野の学習が特に困難で学習障害の影響があるかもしれません。
算数が苦手な学習障害について、詳しくは下の記事をご覧ください。
このように学習障害のある子供は、他の分野の学習はまったく問題なくできるのに「時計を読む」という行為だけが困難な場合があります。
学習障害の症状は個人差が大きいので、周囲にきちんと理解してもらうことが難しく、悩んでいる子も多くいるでしょう。
感覚過敏による影響
2つめに感覚過敏があります。
【感覚過敏とは?】
- 視覚
- 触覚
- 聴覚
- 嗅覚
- 味覚
※五感が敏感で日常生活に支障をきたす状態
感覚過敏の子は時計の時刻がわからないのではなく、時計そのものの見た目や音が気になるため時計を読めないという可能性があります。
カラフルに装飾された時計や、ごちゃごちゃと情報が多すぎる時計は、視覚過敏の方にとっては非常に見づらい場合があるでしょう。
また、針の動く音が「カチカチ」とうるさい時計は、聴覚過敏の方にとっては非常に耳障りで、他のことに集中できなくなってしまう場合もあります。
このように感覚過敏の影響で、時計そのものが苦手で時計が読めないという場合があります。
聴覚過敏について、くわしくは下の記事をご覧ください。
このように時計が読めない理由には、「時計を使って時刻を理解することが困難なケース」と「時計そのものの見た目や音が苦手なケース」があります。
どちらも発達障害のある子供に多くみられる症状です。
では、これから時計が読めるようになるための6つのステップを紹介していきます。
時計が読めるようになるための6つのステップ

苦手な時計を克服するためには、いくつかのステップを踏む必要があります。
まずは次のステップのうち、子供がどの段階にいるのか確かめてみてください。
1.数字を60まで数えられるようになる
2.短針が読めるようになる
3.「◯じちょうど」と「はん」と「5分単位」を理解する
4.長針が読めるようになる
5.短針と長針を合わせて時刻が読める
6.時間の進み方や「◯時間後」などの前後間隔を理解する
子供がどの段階にいるか把握できたら、それぞれのステップごとに練習していきましょう。
1.数字を60まで数えられるようになる
時計を読むためには、60までの数を数えられるようになる必要があります。
数を数えるのが苦手な方は、下記のような方法を試してみてください。
・60個のモノを左から右に移動させながら数える
・日めくりカレンダーのように、紙をめくりながら数える
・5と10のかたまりを理解する
上記のような方法で練習して、60までの数字が数えられるようになったら時計を読む練習を始めます。
2.短針が読めるようになる
まずは短い針の読み方から練習してください。
時計の1〜12の数字の位置に短い針がきたら「◯時」ということを覚えます。
机に向かって覚えるというよりも、「短い針が3のとこに来たら3時のおやつだよ。」などと、日常生活と結びつけながら意識していくと自然に身につきやすくなります。
短針が読めるようになったら、長針の読み方の練習に進みます。
3.「◯時ちょうど」と「半」と「5分単位」を理解する
いきなり長針のすべてを理解しようとするのではなく、まずは「◯時ちょうど」「半」「5分単位」を理解することから始めましょう。
「長い針が12に来たら◯時ちょうど」などと、子供がわかりやすいように丁寧に説明してくださいね。
また、日常生活の中で時計をみながら「今は◯時半」などと意識的に声に出し、定着するまで繰り返します。
これらがしっかりと定着したら、1〜59分までの練習に進みます。
4.長針が読めるようになる
長針の1〜59分までを理解するためには、数字が記載された時計を使用するのがオススメです。
目で見て数字を認識することで、「この位置に長い針が来たら◯分」ということを理解しやすくなるからです。
これが定着したら、ついに時刻を読む練習に進みます。
5.短針と長針を合わせて時刻が読めるようになる
短針と長針それぞれの読み方を習得したら、いよいよ時刻を読む練習を開始します。
短針と長針の両方を見て、「短針→長針」の順に声に出して読んでみます。
両方を見ることで混乱してしまう場合は、まずは短針だけを見て読み、その後長針だけを見て読みます。
こちらもクイズ形式で楽しみながら練習したり、日常生活とリンクさせながら時計を見ることで、自然に身についていく場合もあります。
誰かに答えを聞かなくても、自分で時計を見て答え合わせができるので、意欲があればどんどん吸収できます。
以上の5つのステップで、時計を読めるようになりました。
ここまででも時計を読むことについては十分な場合もありますが、さらに次のステップを理解することで、より一層時間への理解が進みます。
6.時間の進み方や前後間隔を理解する
時刻が読めるようになったら、最後に「◯時間後」や「◯分前」などの前後間隔を理解すると、日常生活の中でとても役立ちます。
時刻を理解した時と同じように、まずは短針から始め、続いて長針に進みます。
だんだんと慣れてきたら、クイズ形式や日常生活の中で自然に定着させていきましょう。
読みやすいオススメの時計

時計を読みやすくするために、まずは発達障害の症状に合わせた「読みやすい時計」を準備しましょう。
発達障害の影響によって、「時計そのものが苦手」だったり、「時計のカラフルな装飾が苦手」だったり、「秒針の音が苦手」など症状は様々です。
これら症状に合わせた時計を準備することで、苦手な時計を克服することにつながるかもしれません。
発達障害のある子にオススメの時計をいくつか紹介していきます。
おすすめ時計①:【マグ】知育時計『よ~める』
まずは壁掛け時計です。
0〜59の目盛があり、1〜12の時間がゾーン分けされています。
赤と青の2色使いで、とてもシンプルな見た目ですが、時間を学ぶのに必要な情報がしっかりと盛りこまれています。
| 価格 | 2,165円(税込)※2022年1月現在 楽天市場最安値 |
| サイズ | 高さ280mm、幅280mm、奥行49mm |
| 本体重量 | 420g |
| 材質 | 樹脂 |
| こんな人におすすめ | 派手な色使いが苦手な人 |
・派手な時計が見づらいと言う視覚優位の子どもが、この時計に変えたらすぐに読めるようになりました。
・◯じとひらがなで書いてあるので、子どもがわかりやすいようです。
・子どもが自分で時計を読めるようになり、自信がついたようです。
・とても軽くて安っぽいですが、安いので仕方ないです。
・チクタク音がうるさいです。
おすすめ時計②:【セイコー】知育目覚まし時計『KR887』
こちらは、時計の学習に最適な目覚まし時計です。
0〜59の目盛りと時間ごとに色わけされたゾーンにより、パッと見て時間を理解できます。
ベル音と電子音の2種類から選べて、電子音は音量の設定も可能です。
秒針がなめらかに連続して動く静音設計なので、聴覚過敏の方にもオススメの時計ですよ♪
| 価格 | 3,542円(税込)※2022年1月現在 楽天市場最安値 |
| サイズ | 高さ8.7cm、長さ13cm、奥行13.4cm |
| 本体重量 | 300g |
| 材質 | プラスチック |
| こんな人におすすめ | 音に敏感な人 |
・0〜59の数字があり、秒も分もわかりやすいです。また、時間もゾーンが色でわかれているので、短い針の説明もしやすいです。
・見た目がかわいく、音も2種類あるので、子どもがとても気に入っています。
・秒針の音がカチカチしないので、とても静かです。
・新しい電池でも時間がずれやすいです。
・アラームが12時間設定なので、オフにし忘れると夜に鳴ることがあります。
おすすめ時計③:【くもん】『NEWくるくるレッスン』
こちらは時計の針を自分で回して時間を学習するための「時計のおもちゃ」です。
本物の時計ではないため、自由に針を動かして時間を学習できます。
「短針は赤、長針は青」と目盛りと同じ色で分けられているので、見た目にもわかりやすい時計です。
| 価格 | 1,650円(税込)※2022年1月現在 楽天市場最安値 |
| 推奨年齢 | 3歳以上 |
| 本体重量 | 320g |
| こんな人におすすめ | 遊びながら時計を学ばせたい |
・子どもが毎日くるくると遊んで時計に興味を持ったようです。
・丈夫な作りで、たくさん回しても壊れにくいです。
・長針が一周すると短針がひとつ進むので、時計の仕組みがわかりやすいです。
・時計の針が太すぎてどこをさしているのかわからないため、真ん中にマジックで線をひきました。
・音声読み上げ機能がついていて欲しかった。
時計が読めなくても時間を守れるようになる4つの方法

ここまでお伝えしてきた方法を試しても時計が読めない場合には、時計を読むことにこだわるのではなく、別の方法を考えましょう。
時計が読めなくても時間を守れるようになるためには、次のような方法があります。
1.デジタル時計を使用する
2.タイマーを利用する
3.行動する時間を時計の絵に書き込んでおく
4.周りの人に時計が読めないことを伝えて教えてもらう
それぞれの方法について、詳しく説明していきましょう。
1.デジタル時計を使用する
アナログの時計がどうしても読めないという場合には、デジタル時計を使いましょう。
数字が読める方であれば、すんなりと読めるかもしれません。
デジタル時計には壁掛けタイプや携帯タイプ、腕時計タイプなどさまざまなタイプがありますので、子供が一番見やすいと思うアイテムを揃えてあげてくださいね。
また、デジタル時計を使う時にアナログ時計を一緒に並べておくと、アナログ時計を見ることが習慣になりやすいのでオススメです。
2.タイマーを利用する
時計を読むのではなく、残り時間を把握するという視点でタイマーを利用する方法があります。
残り時間が表示されるため、次の行動までの時間が把握しやすくなります。
オススメのタイマーは下記です。
タイムタイマー TTA1-W
こちらは残り時間が一目でわかるおしゃれなタイマーです。
文字盤が大きくて見やすいので、どんな方でもパッと見てわかりやすい作りになっています。
カチカチ音が静かな静音設計なので、聴覚過敏の方にもオススメです。
サイズ展開も豊富なので、ご家庭で、学校で、持ち運びに便利なタイプもあります。
| 価格 | 6050円(税込)※2022年1月現在 楽天市場最安値 |
| サイズ | 高さ19.7cm、長さ19.7cm、幅3.2cm |
| 対象年齢 | 3歳から |
| 材質 | プラスチック |
| こんな人におすすめ | 音が気になる人 |
・時計が読めなくても、時間の感覚がわからなくても、残り時間を意識して行動することができます。
・このタイマーをセットした途端、子どもが自分で時間内に準備を完了するようになりました。
・アラームが鳴るので、安心して作業に集中できます。
・値段の割に見た目の質感がよくなかったです。
3.行動する時間を時計の絵に書き込んでおく
時計の絵を使って、行動するべき時間を記入しておくという方法があります。
時刻は読めないけれど、絵と時計を照らし合わせられる子にとっては便利な方法です。
絵と同じ場所に針が来たら行動することで、時間の感覚を意識できます。
4.周りの人に時計が読めないことを伝えて教えてもらう
さまざまなアイテムや方法を使っても、どうしても時間がわからないという場合は周りの人の力を借りることも大切です。
できないことを悩み続けるのではなく、周りの人に打ち明けることでさまざまな面でサポートしてもらいやすくなります。
ひとつの方法にこだわらず、その時の状況にあわせて子供に一番適した方法を見つけてみてください。
しかし、これまでお伝えした方法でも、なかなかうまくいかないという場合には次のような動画を見てみるのもオススメです。
時計の読み方が理解できるオススメ動画
時計の読み方を学習する際に、親子で向きあっているとお互いに煮詰まってしまうこともあるかもしれません。
そんな時は、子供が興味をもちやすい動画を利用するのもひとつの手段です。
ここでは、時計の読み方を理解しやすいオススメの動画を紹介します。
このように、時計の読み方を学習するには段階ごとにさまざまな方法があります。
学習を経て時計が読めるようになる子もいれば、どんなに努力してもどうしても読めないという子もいます。
繰り返しにはなりますが、発達障害は脳の影響によるものなのでご自分を責めたり落ち込んだりする必要はまったくありません。
努力しても時計が読めない場合には、時計が読めなくても困らない方法を考えればいいのです。
まとめ
今回は、「なぜ、発達障害を持つ子供がアナログ時計を読むことが苦手なのか」について紹介しました。
- なぜ発達障害の子供はアナログ時計が苦手なのか理由を解説
- 時計が読めるようになるための6つのステップを紹介
- 読みやすいオススメの時計の紹介
- 時計が読めなくても時間を守れるようになる4つの方法を紹介
訓練して時計を読めるようになれば、子供にとって大きな自信につながり、毎日の生活がより充実したものになるのではないでしょうか。
周りの人たちを味方につけて、時計が読めなくても自分にあった「時間を守れる方法」を見つけていきましょう。