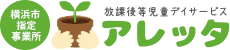今日も皆さんと一緒に発達障害等に関する学びや情報交換の場所なることを願って投稿させて頂きます。
今日のトピックは「発達障害の子供に見られるくるくる回る行動」についてです。
すいか割りをするとき、目隠しをしてから、棒を頭につけてぐるぐる回りますよね。
10回もまわるとフラフラになって、あっちにフラフラこっちにフラフラ、しまいには蛇行し過ぎて尻餅をついてしまったり。船酔いみたいに目がまわってしまい、もうコリゴリと思ったことはありませんか?
しかし、発達障害の子供は目がまわっていてもくるくると回り続けてしまうこともあるようです。
そこで、なぜ発達障害の子供はくるくると回り続けてしまうのか、そしてどんな対処法が適しているのかを解説していきます。
目次
くるくる回る=「常同行動」の可能性?
子供が「くるくる回る」あるいは「ジャンプする」「体を揺らす」といった行動を繰り返すのは「常同行動」(じょうどうこうどう)の可能性があります。
「常同行動」は字の通り、「同じことを繰り返す」ことです。
「くるくる回る」・「ジャンプする」以外にも下記の行動があります。
・コップやお皿をくるくる回す
・手をたたく
・奇声をあげる
・同じルートをいつも通る
・同じ服を着たがる
周りから見ると、同じ行動をしていて飽きないのかな?と思いますが、本人は気にしていない様子です…
こだわりが強いと思われることも多いでしょう。
なぜ、「常同行動」が起きるのか。考えられる3つの理由について説明します。
1.何かを訴えている(伝えたい)
2.刺激がほしい
3.精神的に不安定
1.何かを訴えている(伝えたい)
1つ目の理由として、何かを訴えている可能性があります。
「○○をしてほしい」・「○○を伝えたい」けれども、上手く伝えられない…
伝えられないもどかしさや不満から常同行動を取っているかもしれません。
2.刺激がほしい
発達障害を持つ子供の多くは刺激に対して敏感です。
刺激が弱いと感じると、より強い刺激を求めて常道行動をとる場合があります。
ひたすらくるくる回って気持ちが悪くならないのかな?とこちらが心配になりますよね…
注意しなければならないのは、ケガしないように目を離さないことです。
3.精神的に不安定
発達障害の子供は聴覚・触覚等の感覚が非常に敏感な場合があります。
ちょっとした音や、物の位置間隔のズレがストレスになり、不安や緊張を引き起こすかもしれません。
それらの不安や緊張を緩和・遮断する為に、くるくる回ったり等の常同行動となってしまうことがあります。
発達障害とくるくる回るモノやヒト
発達障害の特徴の中に、【くるくる回る】という項目がありますが、発達障害の中でも自閉症スペクトラム障害(ASD)の子供に多く見られるようです。
子供は活発に動くことが多いので、ふつうの子供でもくるくる回って遊びますが、発達障害の子供の場合は、こだわりが強く親が止めてもくるくる回り続けてしまうことも・・・。
ただし、「くるくる回る」と言っても対象物がモノであったり、ヒト(自分自身)だったりとさまざま。
くるくる回るからといって、必ず発達障害を抱えているとは限りません。
自閉症スペクトラム障害(ASD)についての詳しい記事はこちらです↓
1.自閉症スペクトラム障害(ASD)とくるくる回るモノ
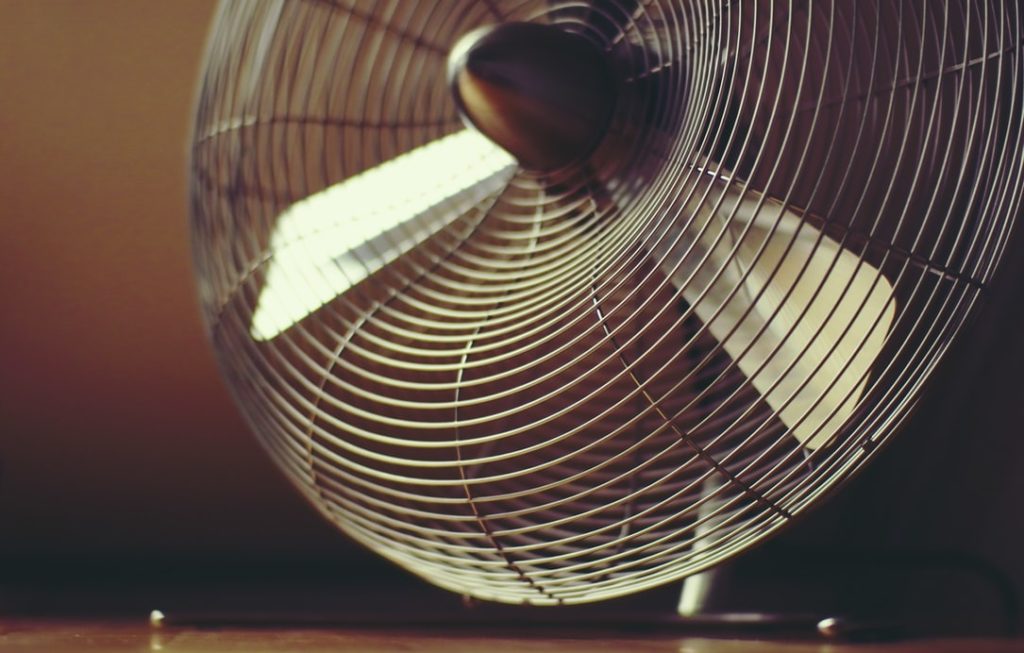
自閉症スペクトラム障害(ASD)の子供の場合は、くるくる回るモノに強い関心を抱くことがあります。
たとえば、おもちゃの車のタイヤをくるくると回すことに集中してしまったり、扇風機が回っているのを、ずっと観察し続けてしまう。
自閉症スペクトラム障害(ASD)の子供は、回っているモノが気になり、首付けになると親が何と言っても岩のようにその場にとどまって動かなくなってしまうことも・・・。
こちらのTwitterでは、指輪タイプのハンドスピナーに「私なら永遠に回してそう」とつぶやかれていますね。
あなたも似たような経験をお持ちではありませんか?
2.自閉症スペクトラム障害(ASD)とくるくる回るヒト

自閉症スペクトラム障害(ASD)の子供の場合は、くるくる回るモノと同じく、自分自身がくるくる回り続けてしまうということもあります。
回り続けていると気持ち悪くなることもありますが、自閉症スペクトラム障害(ASD)の子供は、回り続ければ気持ちが悪くなくなるんじゃないか?と思ってしまうようです。
たとえば、遊園地のコーヒーカップに乗ったとき、面白がってハンドルを勢いよく回して楽しむ。三半規管のバランスが崩れて気持ちが悪くなるけど、楽しいからつい回し続けてしまうことです。
自閉症スペクトラム障害(ASD)のリアルな話が聞ける動画です↓
発達障害の子供がくるくる回る理由

くるくる回ったり、手をひらひらさせたり、ぴょんぴょん飛び跳ねたり・・・。
同じ行動を繰り返すことを常同行動と言いますが、発達障害の場合に考えられる常同行動は以下の理由が考えられます。
【常同行動が見られる理由】
・こだわりが強い。
・安心したい。
・反復動作で刺激が欲しい。
自閉症スペクトラム障害(ASD)の子供は、まわりの音や光に苦痛を感じ、苦しんでいることがあります。
苦痛から不安が沸き上がり、気持ちを落ち着けるために常同行動をとることも。
理由を知ると納得ですよね。
相手を理解しようと思う気持ちは、必ず相手に通じます↓
発達障害の子供と親の葛藤

おもちゃを並べたり、くるくると回ることは、ふつうの子供でもすることがありますよね。
しかし、発達障害の色眼鏡で見るようになってしまうと、途端に不安になってしまう。
自分の不安を解消したいためではないでしょうか?
子供の行動を制止せず、見守ってあげるのも大切ですよ。
くるくる回る子供との付き合い方

くるくる回る子供との付き合い方に、頭を抱えてお悩みのあなた。
無理に止めさせようとすると、子供は余計反発します。かえって不安を感じてパニックになることもあるので、注意してくださいね。また、力ずくで止めてしまうと子供が落ち込んでしまうことも…。
くるくる回っていると足元まで注意が及ばないことがあるので大きな石ころなど、つまずくことが無いか確認してあげましょうね。
1.くるくる回る子供をどうしても止めさせたいとき

見守ることは大事とわかっていても、次の予定まで時間が無くて焦る!ということもありますよね。
あなたの時間だって、子供と同じ。時間は有限ですから。
優しく見守ることが基本ではありますが、どうしてもくるくる回るのを止めさせたいときは、くるくる回る遊びを子供主体にして、あなたも参加してみることが有効かもしれません。
くるくる回る子供を包み込むように抱きしめてあげてから、「お母さんはA君の周りを飛ぶ蝶になるね。ヒラヒラ飛んで、A君が宿題するのを見守っているから、A君も宿題はじめてみない?」「そうしてくれると、お母さんは凄く嬉しいな。」
このように、子供が「くるくる回る」ことから「蝶に見守られている自分」という風に意識が変われば、止められる可能性もあるのかもしれません。
そして、宿題をはじめた子供を見たら、必ず褒めてあげてください。
褒められると嬉しいものです。
全てがうまくいくとは限りませんが、試してみる価値はあるのではないでしょうか。
2.相手の目を見て、ゆっくり話しかける
発達障害による影響で、目や耳から入る情報が定型発達児に比べて劣っている場合があります。何かに夢中になっている時に話しかけても聞こえない様に、聞こえてくる言葉を正しく理解できていないのです。
相手の目を見て、「自分に話かけている」事を自覚させた上で、ゆっくり話しかけましょう。
この際、絵カードを使ってコミュニケーションを取るという方法もおすすめです。
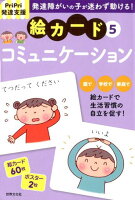
PriPri発達支援 絵カード5コミュニケーションposted with ヨメレバ佐藤 曉 世界文化社 2019年10月04日頃 楽天ブックスAmazonKindle
視覚優位の子供(目からの情報を優先する)の場合、して欲しい動作や内容がプリントされた絵カードを見せつつお願いすることで、情報の整理がしやすくなり、行動に移してくる子供は多くいます。
この絵カードをトピックスにした記事があります。よければ併せてご覧下さい。
施設紹介
発達障害の子供は、あなたの想像を超えた予想外の行動をとることもありますよね。
一人で抱え込むのも辛いものがあります。
もし、発達障害の子供を育てる中で、不安に思ったり心配ごとが出てきたら、放課後等デイサービス・アレッタがあなたのお役に立てるかもしれません。
放課後等デイサービス・アレッタでは、心身に障害のある小学校1年生〜高校3年生までの児童を対象にサービスを行っています。
デイサービスと言っても高齢者の介護とは異なります。障害を抱えた児童や親御さんの休息の場にもなるでしょう。
気になることがありましたら、一度相談してみるのも良いかもしれませんね。

お役立ち情報

発達障害お役立ちトピックスでは、様々なお悩みや症状についての記事を掲載しています。
参考になる情報が沢山あるので、良かったらのぞいてみてくださいね。
まとめ
今回は。発達障害の子供がくるくると回り続けてしまう理由とどんな対処法が適しているのか解説しました。
くるくる回り続ける我が子を見て、船酔いみたいに気持ち悪くなっていないかなと心配になってしまうこともありますよね。
止めさせたい大人とくるくる回り続けたい子供。
平行線をたどるよりも子供の気持ちに寄り添って、対処法を考えてみるとあなたの心も少しだけ楽になるのかもしれません。
ポイントは、優しく見守ってあげること。子供の行動を受け止めてあげるゆとりを持ちましょう!
そのためにも無理は禁物。あなたのことも大切にしながら、子育てと向き合っていただけたら幸いです。