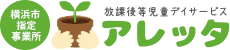今日も皆さんと一緒に発達障害等に関する学びや情報交換の場所なることを願って投稿させて頂きます。
今日のトピックは「発達障害の子供が習い事でふざける場合」についてです。
子供は光る原石。
何かひとつ、子供の才能を引き出してあげたいと思ってはじめた習い事なのに、ふざけてばかりで教室に迷惑をかけているみたい・・・。いつだって、親の悩みはつきませんね。
発達障害とふざけるという行為に因果関係はあるのか?
気になる疑問を丁寧にお伝えしていきますね。
目次
発達障害の子供は習い事でなぜふざけてしまうのか?

子供の悪ふざけは、いつの時代にもありますよね? お友達へのちょっかいがエスカレートして、習い事を中断させてしまうことも・・・。
習い事中の悪ふざけは、子供なりに理由があってやっていて、それ自体を楽しんでいるだけじゃないこともあるんです。
まずは、一般的な子供の心理について考えてみましょう。
発達障害児について助産師のHISAKOさんが語っている動画があるので是非ご覧ください。
悪ふざけの心理
悪ふざけをする心理は大きく下記の2つがあると言われています。ただ楽しいからふざけているだけではないんですね。
- 注目してもらいたい
- 恥ずかしさを隠したい
1.注目してもらいたい
赤ちゃんは関心を集めるために泣きますよね?子供も同じで、周りから注目を集めたいからふざけることもあります。
注目してもらい自分のポジションを確保して、安心感を得ている場合もあるようです。
2.恥ずかしさを隠すため
『裸の王様』という本を読んだことがある方も多いかと思います。見栄っ張りな王様のプライドが、人間の心の弱点を露呈している童話です。
子供の悪ふざけには、王様の心が見え隠れしていることもあるので気に掛けてあげましょう。「怒られないように」「恥ずかしさを隠すために」「不安を取り除くために」悪ふざけをすることもあるんです。
発達障害と子供の行動は繋がっていることが多い

発達障害の子がふざけているように見えてしまうのは、特性の影響だとお伝えしました。
- 注意欠如・多動症(ADHD)の場合
- 学習障害(LD)の場合
- 自閉症スペクトラム障害(ASD)
特性・特徴によって理由と対処が異なりますので、それぞれの特徴について順番に見ていきましょう。
1.注意欠如・多動症(ADHD)の場合
ADHDの特徴は、不注意・多動性・衝動性です。
習い事での悪ふざけと勘違いされやすい行動としては、「落ち着きがなくうろうろしてしまう」「おしゃべりが止まらない」「騒ぎ出してしまう」「話を聞いていないように思われる」などがあげられます。
ADHDの詳しい記事はこちらです↓
2.学習障害(LD)の場合
知能発達には問題はないものの、「読む」「書く」「聞く」「話す」ことなどが困難なことがあります。
ふざけてしまうのは、純粋に理解できないからという理由も。
どうしていいかわからない。周りのお友達は理解しているみたいなのに自分は全く理解できない。取り残されてしまう不安から悪ふざけをしてしまう。
一般的な子供も恥ずかしさから悪ふざけをしてしまうことはありますが、発達障害の子供とは似て非なるものと考えられます。
学習障害(LD)の詳しい記事はこちらです↓
3.自閉症スペクトラム障害(ASD)の場合
コミュニケーションが難しかったり、反復的な行動や活動がみられる障害のことを自閉症スペクトラム障害(ASD)と言われています。
衝動的にもくもくと同じことを続けてしまったり、お友達とのおしゃべりが止まらなくなってしまい、習い事の先生からふざけていると思われてしまうこともあります。
自閉症スペクトラム障害(ASD)の詳しい記事はこちらです↓
その対応についてこれから見ていきましょう!
子供がふざけずに習い事を続ける極意
子供がふざけずに習い事を続けるには、何より子供に寄り添ってあげることが大切です。
- 安心感を与えてあげる
- 完璧を求めない
- 出来たら思い切り褒めてあげる
- 子供の興味を最優先する
こちらの4つの極意についてそれぞれ詳しく解説してきます。
安心感を与えてあげる

ふざけてしまう原因のひとつに、何をしていいのかわからないという理由がありましたよね?
子供の「わからない」という不安をしっかりとフォローしてあげられるように、家でコミュニケーションをとるようにしましょう。
今、自分の子供はどんなことに悩んでいるのかを知ると解決策も見えてきます。
たとえば、スイミングに通っているお子さんが、何をしたらいいのかわからなくてふざけてしまう場合。
先生と連携し、子供がわかりやすい方法を模索していくことや、泳ぎ方を家の中で遊びながら一緒に真似をしてみるなど。子供はゲーム感覚で楽しめるかもしれませんよ。
完璧を求めない
「子供にはこうなってもらいたい」というような理想があるのかもしれません。しかし、発達障害の子供に完璧を求めると子供は逃げ出したくなってしまいます。
海のように広い心で、お子さんを見守ってあげましょう。
それに定型発達の子でも全員が100点というわけではありません。60点取れたら上出来!本人が楽しんでいるからOK!くらいの気持ちでいると楽ですよ。
出来たら思い切り褒めてあげる
誰でも褒められれば嬉しいものです。またそれまでの経験から、発達障害の子供は自己肯定感が低いこともあるので、小さなことでも出来たら思い切り褒めてあげましょう!
子供のやる気にも繋がりますよ。
子供の興味を最優先する
発達障害の子供の特徴として、ひとつのことに集中し過ぎる面があります。
子供の興味がある習い事が見つかれば、集中して取り組むこともできるので、悪ふざけも少なくなるでしょう。
集中できる分、才能が開花する可能性もあるのかも!? ただし、親のエゴで選んではいけませんよ。あくまで主体はお子さんです。
親の気持ち子知らず・・・親が注意すべきポイント

子供には将来こうなって欲しい。だって、子供が大きくなってから不自由させたくないし、幸せな人生を送ってもらいたいから。習い事さえ頑張れば未来は明るい!
そう思っている人はいませんか? これって親の愛ですよね。でも、この考え方には黄色信号がともっていますよ。
親の期待が子供に届くかどうかは別問題。習い事と子供の気持ち、バランスが大切です。まずは、子供の意見や行動を尊重してあげてくださいね。
では、これから発達障害の子供におすすめの習い事についてお話しますね。
発達障害でも習い事はできる!おさえておきたい解決策
発達障害の子供は、ふざけてしまって周りに迷惑をかけてしまうんじゃないかと心配になってしまう気持ち、わかります。
受け入れてくれる教室はあるのかしらと不安になることだってあるかもしれません。
解決策としては、習い事を選ぶときに以下のポイントを確認してみることです。
・子供の発達段階や習熟度に先生が合わせてくれるか
・子供の意欲や主体性を尊重してくれるか
・威圧的な態度ではなく、子供目線で話してくれるか
しっかりリサーチしたら、あとは下記のTwitterの方のように勇気をもってチャレンジしてみましょう!
体験レッスンを利用する
いきなり習い事に通いだすのは、ハードルが高いですよね。お子さんが雰囲気に慣れてくれるか、興味のあることなのか、体験してみないとわからないこともあります。
同じ習い事でも教室や周りの子によって全然違うこともあるので、気になる習い事があったら、まずは体験レッスンがあるかどうか確認してみるのも良いですよ。

子供がのびのび出来るおすすめの習い事【5選】
子供がふざけてしまって習い事が続かない、周りに迷惑をかけてしまうのが申し訳ないと思い、習い事を躊躇している方におすすめの習い事をご紹介します。
発達障害の子供は、マイペースにできる習い事が向いていると言われていますよ。
・スイミング
・ダンス
・ピアノ
・絵画教室
・公文
おすすめの習い事についての動画はこちらです↓
スイミング
スイミングは、個人競技でもあります。区切られたコースの中で、ゴールに向かって泳ぐため、子供が集中しやすいメリットもあります。
ただし、発達障害の子供のなかには、刺激に驚いてパニックになってしまったり、運動の協調性やイメージが低く難しいと感じてしまうこともあるようです。
子供本人の様子を観察しながら習い事にするかどうか決めてくださいね。
スイミングについての詳しい記事はこちらです↓
ダンス

学校の授業でも取り入れられているダンス。
じっとしていることが苦手な子供も、楽しく身体を動かすことができるのでおすすめです。
音楽に興味のある子供に進めてみるのも良いですね。
ピアノ

ピアノは個別レッスンも選べるので、マイペースに進めることができます。先生とのマンツーマンレッスンで、コミュニケーション能力も養えることも。
子供の適性と興味が合えばビックリするほど才能が開花する可能性もありますよ。
マンツーマンは先生との相性がモノを言うので、1回相性が悪そうだと思っても、他の先生にしたら楽しく通えるケースもあるので、いろいろ試してみてくださいね。
また、こんな書籍も発売されています。
| 価格 | 1,540円(税込) |
| 発売日 | 2019/03/17 |
| 出版社 | ヤマハミュージックメディア |
| こんなひとにおすすめ | ・子供にピアノを習わせたい ・発達障害児との向き合い方の参考にしたい |
ピアノについてはコチラの記事でも詳しく解説しています。
絵画教室

絵画教室のメリットは感性が豊かになること。不注意や多動の子供も絵を描くときだけは、驚くほどの集中力を発揮する子も多いようです。
興味があれば一人の世界で楽しく習い事ができるためおすすめです。
公文式

公文式は、発達障害に理解のある先生も多いそうです。(可能な方はこちらも複数の教室を比較されることをおすすめします)
基本的に自分のペースで学習を進めることができるため、教室の雰囲気があっていれば、子供にとって居心地の良い習い事になるかもしれませんね。
公文式オフィシャルサイトはコチラからご覧ください。
施設紹介
発達障害の子供を育てる中で、不安に思ったり心配ごとが出てくることもあると思います。そんなときは、放課後等デイサービス・アレッタがあなたのお役に立てるかもしれません。
放課後等デイサービス・アレッタでは、心身に障害のある小学校1年生〜高校3年生までの児童を対象にサービスを行っています。
デイサービスと言っても高齢者の介護とは異なります。障害を抱えた児童や親御さんの休息の場にもなるでしょう。一度相談してみるのも良いかもしれませんね。
お役立ち情報

発達障害お役立ちトピックスでは、様々なお悩みや症状についての記事を掲載しています。参考になる情報が沢山あるので、良かったらのぞいてみてくださいね。
まとめ
- 子どもが悪ふざけするのは、「注目を集めたい」「恥ずかしさ・不安を隠したい」といった理由もある
- 発達障害の場合は特性によりふざけているように見えてしまうケースが多い
- 特性に合わせた習い事の種類や、先生・教室との相性をみて選ぼう
今回は、発達障害の子供がふざける理由と解決策についてお伝えしました。
子供がふざけてしまうのは、発達障害がかかわっていることもあるんです。まずは、子供の興味を優先してあげること。そして、子供に寄り添って常に一緒に考えるスタンスでいることが、上手くいくコツだと思います。
お子さんの未来が明るいものになるように、温かい心で見守ってあげましょうね。あなたの思いが希望に変わりますように♪
最後までお読みいただきありがとうございました。