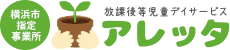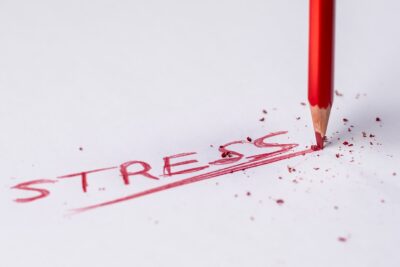皆さんこんにちは!本日も発達障害等に関する学びや情報交換の場所となることを願って投稿させて頂きます。
今日のトピックは、「発達障害の子どもを持つ親のストレス」です。
他のどのストレスよりも、子どもを育てる時に感じるストレスはとても大きく、発達障害を持っている子どもの親はさらに多く感じるでしょう。
ストレスが溜まり過ぎてどうすればいいかわからない時や負の無限ループに入ってしまう時もいっぱいありますよね。
多くの保護者がどのような時にストレスを感じるのかを共感しながら、どのようにしてストレスを解消できるか、参考にしてみてください。
目次
発達障害児の親御さん…こんな時にストレスを感じる!
どんな時にストレスを感じますか。
実は、発達障害児の親は健常児の親に比べて、何倍もストレスを感じながら育児をしています。
しかし、発達障害児の保護者の中で、「何がストレスに感じるのかわからない」「はっきりとしないけど大きな不安がある」「とりあえずわからないことだらけで困惑してる」と感じている方は少なくありません。
まずは、自分にどんなストレスがあるのか理解していきましょう。以下に挙げる内容の中でどれが自分に当てはまるのかを確認しながら読んでみてください。
参考文献:現在の発達障害における母親の精神的ストレスについて
子どもに対して

子どもの問題行動は、多くの保護者が感じるストレスです。
発達障害の子どもは、独自のこだわりやルールを持っていたり、発語が少なかったり、自分の感情のコントロールすることが難しく、保護者でもわからないことが多いですよね。
そのため、急に走ったり叫んだり、物を投げたり他人を攻撃したり、自分を傷つけたり、様々な突発的な行動をします。いくら注意をしても話しても、特に年齢の小さい子は中々理解できず、また同じ行動を起こします。
このようなことが続くと、外出するのを控えるようになったり、近所の人に会うのが恥ずかしかったりする方は少なくありません。
また、兄弟がいる場合、発達障害児の兄弟に対する態度や、その子自身の将来で不安や心配が重なることでもストレスが溜まります。
そのように感じる親はあなただけではありません。多くの親が、子どもに対する上記のようなストレスを抱えているのです。
周囲に対して
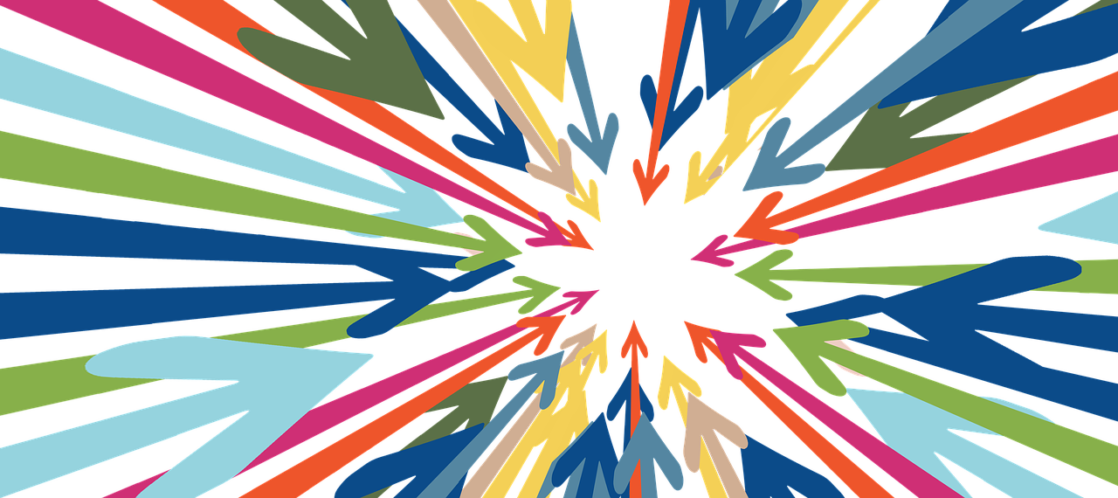
続いて、周囲の理解や助けのなさにストレスを感じます。
特に多いのは、夫や家族が子どもの発達障害に関する症状や程度を理解してくれなかったり、自分の教育の仕方が悪いと責めてきたりすることです。
ご存じの方も多いですが、しつけの仕方が悪いから発達障害になるのではありません。現在、発達障害は先天的である考え方が一番有力であり、遺伝的要素と環境的要素が複雑に絡み合うことで発症します。
以前よりはメディアなどで取り上げられることが多くなったとは言え、まだ理解が少ない人もいます。そして、それが身近な家族だとさらに母の孤独感がとても大きくなるでしょう。
また、それが学校の先生や近所の人がそうであると、何でわかってくれないのかという苛立ちもこみ上げてきてストレスは増える一方ですよね。
自分に対して

最後に、上記の2点よりもさらに多くのストレスを感じるのは、自分に対してです。母として一番子育てに責任を持っているので、自分に対するストレスも多いのでしょう。
- 発達障害を持ったのは自分のせいだ(妊娠中の行動やしつけがいけなかったのか…)
- 自分がもっと早く気づいてあげれれば、もっと早くから対応しておけば…
- 何でイライラに任せて子どもに当たってしまうのだろう
- 自分の子どもが発達障害であることが恥ずかしい、自分の子どもが劣っていると感じてしまう
一つずつ挙げていったらきりはありませんが、このように考えたことがない保護者、特にお母さんはいるのでしょうか。ほとんどのお母さんはこのストレスと毎日向き合いながら育児をしています。
自分にはどんなことができるの?

まずは、そのようなストレスを自分でどのようにコントロールして育児をしていけばいいのでしょうか。
多くの方が実践してよかったと言われていることをいくつか紹介します。始められることから実践してみましょう。
自分の意識を変える
ストレスはマイナスなことだと捉われがちですが、ストレスは自分の想定したように物事が進まないと起こります。そのため、ストレスがあることは、それだけ責任を持って子育てをしたい気持ちの表れであるという風に見てみましょう。
意識を変えれば、「自分に対するストレス」で述べた多くの考え方が変わっていきます。
- 過去のことで悩むのではなく、これを学びとして同じことを繰り返さない
- 今気づけたんだからこれからどうすればいいか調べてみよう
- イライラの元は何か探そう、イライラが溜まっている時は深呼吸をしよう
- 自分に自信を持つことで自分の子どもにも自信が持てる
一例ですが、少しだけ考える点をずらすことで意識が変わります。意識が変われば、次に取る行動も変わって、その変化は子どもも感じるでしょう。
たくさんの保護者がストレスに感じる問題行動も、見方を変えればその子の長所に変えられます。保護者が意識を変えれば、状況も変わっていきます。
よく「発達障害は個性!」とおっしゃる方を見かけますが、個性としてそのままにするのではなく、その個性を活かして普段の生活に支障が生じないようにするために、何のサポートが必要かという風に意識を変えてみましょう。
子どもの今の状態を認める

健常児や他の発達障害児と比べず、その子の現状を認めてあげてください。
子どもに対するストレスは多いです。しかし、ほとんどの場合は周りと比べずにその子を受け止めて上げれるだけで、解消することも多いです。
前の項目とつながる部分がありますが、「何歳なのに〇〇ができない」「療育に通っているのに症状が良くならない」などと不安になる気持ちはわかります。しかし、今その子ができることに目を向けてみてください。
1年前や半年前と比べて、少しでもできるようになったことはありませんか。そこをちゃんと褒めていますか。認めていることを言葉にしてあげていますか。
言っても聞かない、理解しないと思うのではなく、表情やハグなどの非言語表現を使って、その子への愛情を示して見てください。徐々に、子どもがそれを感じ取り、同時にその子の自己肯定感を高めることにもつながります。
周りに助けを求める
自分だけで頑張っても解決できないこともあります。また、自分だけで頑張り過ぎて、ストレスを解消するための行動が返ってストレスを溜めてしまうこともあります。
初めは自分でできる所までやって、少し難しく感じたら周りに助けを求めましょう。まずは、子どもがどんな発達障害なのか、どういう行動をする可能性があるのか、症状の程度はどのくらいなのかを説明する所から始まるかも知れません。
しかし、説明するだけでも周りの手伝う姿勢は変わります。
どんな助けを求めていいの?
では、どのように助けを求めればいいのでしょうか。
先ほどの動画では述べられていなかったことをもう少し詳しく見ていきましょう。すでに実践している方もいるかも知れませんが、今一度確認して見てください。
家族で助け合う

一番理解してもらいたいのも、一番協力してもらいたいのも家族ですよね。
大事なことなので繰り返しになりますが、 まずは、子どもがどんな発達障害なのか、どういう行動をする可能性があるのか、症状の程度はどのくらいなのかを共有しましょう。
一緒に診察に行ってもらったり、一緒にこの記事を読んでもらったり、一度子どもを観察してもらったり、理解を得られるための方法はたくさんあります。
重要なのは、押し付けたり今までのことを責めるのではなく、これから協力するためにお互いが何をすればいいのか、その子の将来どうなって欲しいか(自分だけで身の回りのことができるようにするなど)を明確にすることです。
どれだけ育児に熱心で子どもに愛情があっても、言葉にして目標を明確にしなければ、家族で意見がぶつかってしまいます。診てもらっている医者からアドバイスをもらってから決めてもいいでしょう。
公的な支援や制度を利用する
すでにご存じの方はいるかも知れませんが、どのような支援や制度があるのか見てみましょう。内容は地域によって異なる場合もありますので、役所などでしっかりと確認してください。
児童発達支援
小学校に上がる前の6歳までの発達障害児を対象にした支援です。認可されれば、お住いの地域の児童発達支援事業所や児童発達支援センターで支援を受けられたり、発達障害児の教育の相談ができたりします。
療育手帳や身体障害者手帳、精神障碍者保健福祉手帳を持っていなくても、障害児通所給付費支給申請を専門家の意見書などと一緒に提出し、児童発達支援利用の必要が認められれば、受給者証が市町村から発行されます。 引用元:りたりこ発達ナビ 発達障害のこと
専門的な機能訓練を行ったり、通える保育園などの訪問を手伝ったり、一時的に子どもを預かったり、様々な施設があります。各ご家庭の要望や必要性に応じて、どのような支援を受けたいかを相談してみましょう。
療育手帳
都道府県知事が発行する、知的障害者が支援を受けるために必要な手帳であり、自閉症など他の発達障害がメインであっても知的障害もあれば申請できます。
療育手帳を持っていることで、子どもに適した療育を受けられるだけでなく、税金の控除、交通機関や公共料金の免除または割引など、保護者にとっても大きな支援です。
加配制度
発達障害児を受け入れる保育園で実施されえている制度で、発達障害児が保育園での生活に慣れるための必要なサポートをするための先生を加える制度です。基準は自治体によって異なりますが、保護者か保育園が申請をします。
一人の発達障害児に一人の先生というよりは、加配の先生が入ることでそのクラス全体をサポートする形になります。希望したい場合は、まず保育園の先生に相談してみましょう。
特別児童扶養手当
発達障害や身体障害を持っている人が受けれる手当です。共働きでなければ金銭的に厳しい家庭がほとんどだと思うので、この手当は必ず申請して、金銭的な不安を解消しましょう。
学校に相談する

先ほどの動画にもありましたが、学校との連携は不可欠です。担任の先生や特別学級の先生、スクールカウンセラーに相談するといいでしょう。
学校での態度や様子を報告してもらったり、気を付けて欲しいことを伝えたりすると、上手く連携が取れます。
勉強面は、学校だけでカバーできないことがあります。その場合は、発達障害の子ども向けの個別指導塾や家庭教師、通信学習もあるので、それらも活用してみてください。
発達障害児の親のコミュニティーに参加する

健常児もいる学校に通っていると、子どもの友達の保護者に理解できない悩みや相談事があります。近所の人も協力的であっても、完全に理解してもらうには時間もかかるでしょう。
そのような時は、発達障害児の親のコミュニティーや療育センターの育児サークルに参加してはいかがでしょうか。役所や療育施設に聞くと、開催の詳細を教えてくれるます。
周りに悩みを理解してもらえないと、どうしても孤独感は取り除くことが難しいです。そのため、似たような境遇や経験をしている方々と話す機会が増えれば、ストレスが解消できます。
また、仲良くなった方たちと集まったり出かけたりすれば、気分転換にもなり、より育児に集中できるでしょう。
まとめ
- 発達障害児の育児はほとんどの面でストレスがある
- それらのストレスをコントロールするために自分でできることは、自分の意識の変化と子どもの現状を認めることである
- 周りに助けを求められるので、一人で無理をしない
- 家族の協力、公的支援や制度の利用、学校との連携、他の発達障害児の親との交流を活かす
育児に責任を持って頑張っているからこそ、ストレスがあるので、落ち込む必要はありません。
意識の変化はすぐにできない方もいるので焦らず、周りの協力を得ながら少しずつ変えていきましょう。
本日も最後まで読んで頂きありがとうございました。