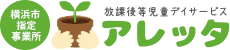今日も皆さんと一緒に発達障害等に関する学びや情報交換の場所なることを願って投稿させて頂きます。
今日のトピックは「発達障害とくもん」についてです。
発達障害があると、子供の将来が不安になってしまいますよね。
少しでも知識や知恵をつけてあげたいと思うのが親心だと思います。
くもんは他の学習塾とは違い、発達障害の子供でも比較的学びやすい環境なのでは?と思い、メリットとデメリットを合わせて調べてみました。
目次
発達障害の子供にくもんは有効?

くもんの学習スタイルは、基本的に自主学習です。
発達障害の度合いや症状によって、くもんとの相性も変わってくるもの事実。
学習が楽しい!褒められるのも嬉しい!という子供にはおすすめです。
子供の特性や気持ちによって左右されるところはありますが、向き不向きはあるようですね。
では、くもんの詳しい特徴について見てみましょう!
くもんの特徴
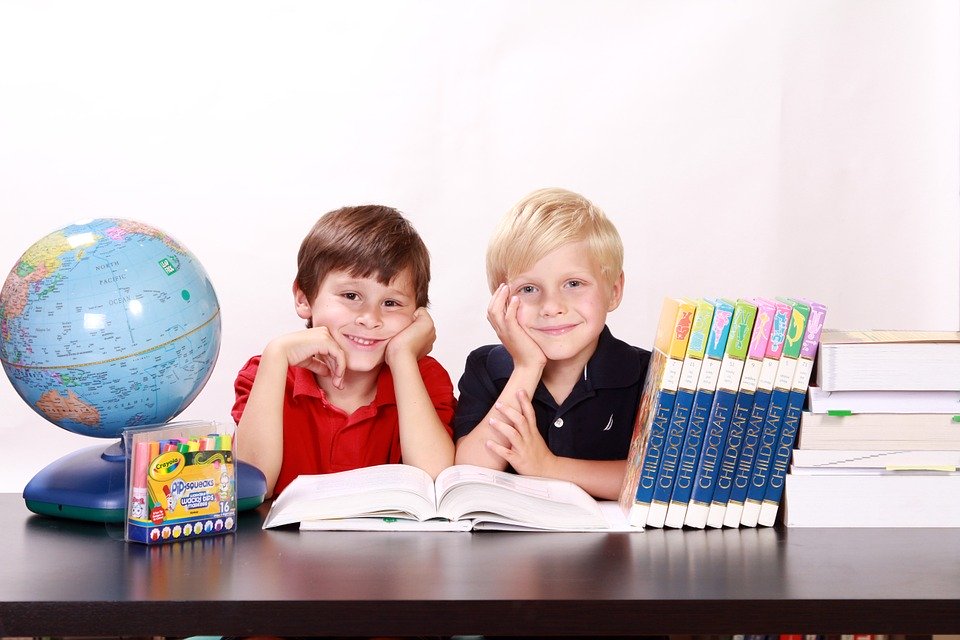
くもん式は、文字や数字を読むレベルから、大学の教養課程レベルまで小さなステップで構成されています。
好きなこと、興味のあること、得意なことってありますよね?
くもんでは、障害がある人に優しい取り組みもあるんですよ。
それは、能力を高めていくことで「障害の特性」を相対的に小さくするということ。
学習では、無理なく進められるのが最大の特徴ですね。
1.障害の特性ってどんなこと?
障害の特性について、わかりやすくお伝えしますね。
障害がバスケットボールの大きさだとして、能力がバスケットボールを自分の腕で抱えている範囲だとします。
くもんで楽しく学習をして能力が伸びた子供は、バスケットボールから卓球のボールの大きさに変化!
小さくなっちゃいましたね。
卓球のボールを同じように自分の腕で抱えたら、余白がたくさんできます。
ということは、能力が障害を包み込んでいるということになりませんか。
障害というボールが小さくなると、腕の中のボールは目立たなくなり、逆に能力が大きく見えます。
くもんで学習を続けると意外な才能が開花するかもしれませんね。
発達障害の症状別の問題点

1.くもんと自閉症スペクトラム障害(ASD)
自閉症スペクトラム障害(ASD)の子供は、集団行動が苦手です。
自分の気持ちも上手く伝えられない子供も多いので、先生に質問できず悩んでしまうことがあるのかも。
臨機応変に対応することが難しいため、普段と違うことがあるとパニックになる可能性もあります。
抜き打ちテストが良い例ですね。
くもんは、宿題を自宅で行いながら、定期的に教室でも学びます。
子供が学習をする中で、わからなそうな部分はどこなのか気にかけながら進めてみると良いですよ。
わからないことを質問できない子供でも、こちらから聞いてあげることで安心感を与えてあげられます。
自閉症スペクトラム障害(ASD)についての詳しい記事はこちらです↓
2.くもんと注意欠陥・多動性障害(ADHD)
おしゃべりが止まらなくなってしまうこともあるADHD。
周りのお友達の学習を妨げてしまうこともあり得ます。
じっとしていられなかったり、気が散りやすいので集中して学習することが難しいかもしれません。
くもんで学習するには、気が散る要素を取り除くことも大事。
壁の掲示物に気を取られない場所や静かで落ち着いた場所を選んでみるものいいですね。
ADHDの詳しい記事はこちらです↓
3.くもんと学習障害(LD)
知的障害はなくても、読む・書く・計算するなど苦手なことが多いのも学習障害(LD)の特徴。
覚えることが困難で、文字が読めずに苦戦することもあるかもしれません。
一度学習しても忘れてしまうこともあるので、先生に何度も教えてもらいながら繰り返し学習していくことが必要です。
学習障害(LD)についての詳しい記事はこちらです↓
くもんのメリット

くもんの学習でできることが増えてくると、自発的に「もっと学んでみたい」という思うが芽生えてくるのかもしれません。
くもんのメリットは以下の通りです。
- 学習のリズムができる
- マイペースでいい
- 子供の才能を伸ばせる
ではそれぞれ説明していきます。
2.学習のリズムができる
発達障害の子供はこだわりが強いので、お風呂に入る時間など必ずこの時間じゃないとダメ!ということがあります。
くもんは、発達障害の子供の特性を良い方向へ変えることもできるのかもしれません。
小さなことでもコツコツ積み重ねることで、「自信」や「やる気」が向上していくかもしれませんね。
3.マイペースでいい
みんなで集まって話を聞くのが苦手な子供もいますよね?
くもんでは、先生の話をみんなで聞くこともないので、自分のペースで学習を進められます。
また、「今できる」ことをマイペースに進められるため、周りに合わせることなく学習することが可能です。
4.子供の才能を伸ばせる
子供には向き不向きがあると同時に、才能が眠っていることもあります。
全く文章を読まなかった子供が、くもんの学習を進めることで国語が好きになることだってあるかもしれません。
くもんのデメリット

くもんのデメリットは以下の通りです。
- 費用が高い
- やる気がないと続かない
- 周りが気になる
では、一緒に見ていきましょう!
1.費用が高い
地域や年齢によっても異なりますが、くもんの1教科の月額会費をご紹介します。
| 東京都・神奈川県に所在する教室 | 左記以外の地域に所在する教室 | |
| 幼児・小学生 | 7,700円(税込) | 7,150円(税込) |
| 中学生 | 8,800円(税込) | 8,250円(税込) |
| 高校生以上 | 9,900円(税込) | 9,350円(税込) |
入会金は不要ですが上記のように、1教科7,150円~9,900円ほどするようです。
また、英語学習時は専用リスニング機器「E-Pencil」6,600円(税込)を購入する必要があるので10,000円以上かかる場合もあります。
金額以上にメリットが大きいと感じたら、試してみるのも良いのかも!?
2.やる気がないと続かない
自ら進んで行うことで、子供の知識も積み重なっていきます。
自主性の求められるのが「くもん」。
やる気がないと、思うような効果は見られないのかもしれません。
「できない」「宿題が多すぎる」などお子さんの口から出るようになったら、一緒に考えてあげることも大事ですね。
3.周りが気になる
やはり、色んな子供がいる中での環境は、発達障害の子供には少し刺激が強い場合もあります。
周りが気になってしまい、集中できないことも多々あるかもしれません。
また、静かな空間に耐えられず、動き出してしまうことも考えられます。
くもんを始めたいけど迷いもある!不安解消法

くもんのメリットとデメリットを知って、子供に習わせたいと思うけど子供に合うか心配。
楽しく学習してくれるかな。
周りのお友達に迷惑をかけてしまわないか不安。
発達障害の子供というだけで、心配ごとは尽きません。
どんな子供でも個性があって、みんな素晴らしい子供。
だからこそ、思ったことはチャレンジしてみても良いのではないでしょうか?
これから、あなたの不安を少しでも軽減できるような方法をご紹介しますね!
1.くもんの本で興味をリサーチ
発達障害でじっとしていられない我が子を教室に通わせるのが心配。
同じような思いをされているお母さんもいますよね。
くもんから本も出ているので、教室に行くにはちょっと・・・と思うなら、試してみるのも良いかもしれませんね。
お子さんの興味を確かめてから、教室へ行ってみることもできると思います。
おすすめの本はこちらです↓

くもんのはじめてのおけいこposted with ヨメレバ くもん出版 2014年10月14日 楽天ブックスで探すAmazonで探す
【楽天ブックス くもんのはじめてのおけいこ】
鉛筆を自由に使いこなせる基本運筆力をつけます。
総合評価 4.35/23件 価格 726円(税込)
【良い口コミ】
・書きやすく、なぞりやすく、鉛筆を持ち始めて間もない子にはやりやすい教材だと思います。
・子供が遊びながら楽しく落書きが出来ます。
・線をひくのが楽しくてどんどんやりたがります。【悪い口コミ】
引用元:楽天ブックス
・1日1枚が集中力の限度のようです。
くもんに入会するには?

くもんに入会するには、いくつか方法があるのでまとめてみました。
- 無料体験学習を利用する
- 教室を見学する
- 希望の教室ページ(ウェブ)から予約する
おすすめは無料体験学習を利用することですが、それぞれ説明していきます。
1.無料体験学習を利用する
くもんでは、2月・5月・11月の年3回無料体験学習を開催しています。
期間中は1週間、教室で計2回まで1教科から希望に合わせて無料体験学習ができ、教材費などもすべて無料です。
また、くもんのサイトに登録しておくと無料体験学習の受付開始をメールでお知らせしてくれます。
メアドを入力するだけで登録できるので、興味がある人は下のサイトから登録してください。
2.教室を見学する
教室を見学する場合は、希望の教室の教室見学をウェブで予約します。
見学日は、教室時間中や教室日以外に見学できるなど教室によって様々です。
なので、予約の際教室の先生と相談が必要になってきます。
お近くの教室を検索できるので、下のサイトからご覧ください。
3.希望の教室ページ(ウェブ)から予約する
希望の教室のページ(ウェブ)から初回の訪問日を予約します。
受付後、指導者から連絡がありますので相談の上、訪問日を決めます。
下のサイトから入会までの流れ、会費・手続きを説明していますのでご覧ください。
施設紹介
発達障害の子供を育てていると、学習以外にも不安や悩みが出てくると思います。
こちらの施設で相談することもできるので、良かったらご覧ください↓

放課後等デイサービス・アレッタでは、心身に障害のある小学校1年生〜高校3年生までの児童を対象にサービスを行っています。
デイサービスと言っても高齢者の介護とは異なります。障害を抱えた児童や親御さんの休息の場にもなるでしょう。
気になることがありましたら、一度相談してみるのも良いかもしれませんね。
お役立ち情報

発達障害お役立ちトピックスでは、様々なお悩みや症状についての記事を掲載しています。
参考になる情報が沢山あるので、良かったらのぞいてみてくださいね。
まとめ
今回は、発達障害とくもんについて解説しました。
くもんて良さそうだけど、発達障害があるから・・・と諦めていた方は、一度チャレンジしてみるのも良いですよ。
子供によって合う合わないがあるので、きちんと見極めてあげることも大事。
チャレンジしたけど、ダメだったということもあるでしょう。
しかし、「行動する」「してあげる」ことは、必ず子供の糧となりますよ。
くもんの勉強法が発達障害のお子さんのヒントになれば幸いです。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。