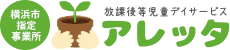今日も皆さんと一緒に、発達障害等に関する学びや情報交換の場所となることを願って投稿させて頂きます。 今日のトピックは「発達障害 人見知り」についてです。
他の子に比べてうちの子は人見知りが激しい気がする
どの程度人見知りだと発達障害なの?
幼児期になると、少しずつ家族以外の人と交流する機会が増えてきます。その中で、コミュニケーションをとるのが苦手な子が出てきます。これは、性格の問題?それとも発達障害?
今回の記事は、このような疑問をお持ちの方に読んでもらいたい内容になってますので、最後までぜひ読んでください。
目次
そもそも人見知りが症状の障害とは?
代表的な発達障害として、自閉症、アスペルガー症候群、ADHD(注意欠陥多動性障害)、LD(学習障害)があります。
人見知りが症状の障害は、自閉症とアスペルガー症候群です。両者は似ている部分が多く同じ部類に入りますが、共通している点として、人と人との関わりを持つことが難しい障害です。
次に症状が出始める時期について解説します。
発達障害の症状が出始める時期

発達障害は早くて1歳頃から兆候が出てきます。代表的な発達障害である、自閉症、アスペルガー症候群、ADHD、LDは3歳頃から症状が現れ始めます。3歳になると、少しずつ言葉を覚え始め、家族以外と接する機会が増えてきます。では、1歳、3歳、7歳ごとに兆候を見ていきましょう。
1歳頃の発達障害の兆候
1歳頃になりますと、親の声に反応したり、声を発する、手を振る、手足をばたつかせる、などができるようになる頃です。発達障害の兆候として、
- アイコンタクト
- きょうだい以外の同い年くらいの子への関心
- 微笑み返し
- 名前に反応する
- 人見知り
1歳半までに
- 興味による指差し
- 大人の指さしたものを目で追う
- 大人の視線の先を目で追った後、大人の顔を見る
- 興味のあるものや見てほしいものを、大人に見せに来る
- 簡単な指示を、身振りがなくても言葉だけで理解する
- 身近な大人の言葉を真似する
これらの行動が見られなければ、発達障害の可能性があります。
厚生労働省が定めた1歳半検診で判明することもあります。上に挙げた兆候を注意深く観察し、1歳半検診の際に先生に相談してみましょう。
3歳頃の発達障害の兆候
発達障害へのアプローチは、早ければ早いほど障害による生きづらさを軽減することができます。3歳までに始めることが望ましいです。
3歳頃の発達障害の兆候として、
- 人見知りが激しい
- 感情が爆発しやすい
- 新しい環境や人を極端に嫌う・不安がる傾向がある
- 気に入らないことがあると、すぐに暴力を振るう
- 同じくらいの年の子と遊べない
- 衝動的な行動が多い
- ごっこ遊びをしない
- 聞かれたことに対して答えられないことが多い
- 会話が成り立たない
- 言葉が遅れている
- 気に入った遊びだけを続ける など
この中で、4、5個当てはまるようでしたら一度専門家に相談してみた方が良いかもしれません。人見知りが激しいだけですと、単に内向的な性格なのかもしれません。自閉症は極度の人見知りも症状の一つですが、発達障害は複数の行動の特徴や症状を持っていることが多いため、他にもおかしいと思う行動はないかチェックする必要があります。
7歳頃の発達障害の兆候
7歳頃になりますと、小学校に入学し、本格的に社会生活が始まるので、兆候が表れやすくなります。このころの兆候として、
- 授業中、どこを見ているのか分からず、ぼーっとしている
- 椅子に座っていられない
- 初歩的な計算ができない
- 言われた内容や読んだ内容が理解できない
- 好きなものには集中し、理解が早い
などが挙げられます。放置したままですと、大人になるにつれて、どんどん生きづらさを感じてしまうので、早めに対処しましょう。
参考元 発達障害の特徴って何?0歳|3歳|7歳|年齢によって違いはあるの? 【医師監修】3歳児の発達障害チェックリスト!早期療育のメリットも
乳児期の子供のほとんどは人見知りをする
実は、乳児期のほとんどの子供が人見知りをします。これは心を許している親と他人を区別するための愛着行動の現れで、成長の過程だと言われています。親が自分から離れてしまうと途端に泣いて追いかけてくるのもその一種です。
ですが、発達障害の子供は、自分と相手との関係性が理解していないことが多く、誰に抱っこされていてもにこにこしていたり、逆に、人見知りが激しく、親以外の人と関わることを極端に嫌うことがあります。
参考元 子育て情報コラム
極度の人見知りでも障害ではない場合も
一般的に人見知りは生後7か月頃から現れると言われています。2,3歳頃までで親との愛着関係を築き、その後に他人とも触れ合っていくのですが、中々上手く関係を築けない子もいます。
そのような子には、まず無理に知らない人の輪に入れるようなことはやめましょう。周囲がその子を理解しようとする姿勢も大切です。
その子なりのペースで徐々に慣れてもらうのが良いでしょう。そうすれば、緊張がほぐれ、自信が持てるようになり、自分の気持ちも表現できるようになります。
見極めのポイントとして、年齢に応じたコミュニケーションができるかに注目してみましょう。親の言葉が理解できるか、自分の意思を伝えられるか、周囲の状況に合わせて行動できるかがチェックポイントになります。
過度な心配はせず、愛情を注ぎつつ、注意深く見守りましょう。
参考元 子育て支援コラム 2歳の子どもが極度の人見知り 病気の可能性は?
人見知りは育て方に問題があるからではありません
自分の子どもが、人見知りが激しいと、自分の育て方が間違っていたからだと思うかもしれません。ですが、もともと周囲の環境に敏感な性格であったり、知らないものへの不安や警戒心が強い性格など、もって生まれた性格が背景にあります。
他の子の輪の中に入れてしまえば、人も知りは治るだろうという安易な考えは絶対にやってはいけません。中には、そのような荒療治な方法で人見知りが改善する子どももいますが、多くの子どもは、このようなやり方を苦痛に感じています。
このような経験がきっかけで、大人になっても人との関わりが苦痛で、心を開けなくなってしまう可能性もあります。
1月のテーマ:子どもの特性について~人見知りが激しい子どもへの対処法~
うちの子が発達障害だとわかったら
自分の子どもが発達障害だとわかりましたら、早めの療育が大切です。療育で障害が治ることはありませんが、訓練を重ねることにより、社会性や人との関わり方を学ぶことで、生きづらさが軽減されます。
まずは、お近くの福祉センターに相談してみましょう。また、かかりつけの小児科や発達障害専門の診療医師がいる病院に相談しても良いでしょう。そこで、療育や受け入れてくれる学校が見つかるかもしれません。
まとめ
人見知りは成長の過程で多くの子供が経験します。発達障害かそうでないかを見極めるポイントは、年齢に応じたコミュニケーションや適応能力があるかで判断してみましょう。
また、保育園や幼稚園の先生、地域の保健師の方とも情報を共有すると、相談するだけで心が楽になりますし、一人で背負い込まないことも大切です。
過度に心配せずに愛情をもって接しつつ、注意深く見守っていきましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。